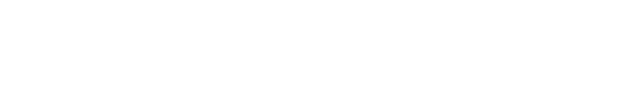自殺対策
「痛みにより救われる症例」、嗜癖としての痛み、および自殺対策としてペインクリニック(非精神科)にできること」
Ⅰ.痛みにより救われる症例について
60代女性。右顔面痛を訴え受診。右三叉神経第2、3枝領域に移動性の痛みがあり、食事、会話などによるトリガーはなく、タッピングによる放散痛も認められない。
非定形顔面痛と考え、外来および入院にて星状神経ブロックを施行した。テグレトール、トリプタノールなど当時において神経障害性疼痛に効果があるとされた薬剤を数種類試すも効果は全くなかった。星状神経節ブロックも2週間連日施行されたが無効であり、退院時においても痛みの軽減はなかった。
外来初診の話であるが、きちんとした身なりの初老女性が診察室に入ってくる。その後ろには40歳くらいの男性が、うつむきながら続いてきて息子と思われた。
患者は丁寧な態度で、表情にまだ余裕の残る笑みを軽くだが浮かべつつ、痛くて困っていますとその窮状を訴えられる。痛くて何もできない状態で、夜も眠れないと。ただその表情には他人を気遣う配慮のような余裕が、まだ残されている。痛みの外来でよくある、苦痛によって眉間に皺の寄る表情とは異なっている。その女性患者の育ちが良く、品性のあったからだけかも知れないが、初診の第一印象としては不自然な印象を持った。
話を聞く中で、2週間前に患者の息子が鉄道に飛び込み、自殺されたことを聞き受けた。その時の患者の様子は、淡々とだがやや寂し気な感じではあったが、それ程ひるむような感じでもなく、ある意味堂々とされていた。患者の話はさらに続き、半年前に病気で夫が亡くなり、それがその息子には相当ショックであったという。また患者の後方に座る男性はその自殺された息子とは双子の弟にあたるということであった。その弟である方は、ずっとうつむき加減に座られて、あまり診療の会話に入ってくる様子も無く、暗い表情が窺われていた。家族が最近自殺されたということを考えれば至極当然ではある。患者である母親は、小さい子供の前でしっかりとした模範を見せなければといったmaternal affection(母性愛)から生ずるとも思われるしっかりした態度であり、どちらかというとその弟の方が患者ではないのかと思われるような男性の表情のであった。
まだ喪も明けないうちに来院され、その初診での問診は終始穏やかに行われ、患者のときに丁寧な相手を気遣うような笑みを浮かべつつ、それでもやはり根底にはその不幸な現実からくる悲嘆さなのか、硬い表情が垣間見られた。そして、痛くて困ってるのです、どうにかして下さいということであった。
考察
当初は、いわゆる適応障害のような、ショックな出来事に付随した一時的な身体症状や悲哀反応と考え、抑うつ症状が痛みの閾値を変化させた結果として痛みを訴えていると考えていた。
三環系抗うつ薬を低用量からはじめ、医師-患者治療関係を十分に留意した。それについては、10年ほど後にある市民講演会で講演をした際に、その患者が聴講されており、終わり際ににこやかに近寄ってこられ話しかけられたのだが、その印象でも治療関係は十分以上のものがあったと思っている。入院中の支持的な精神療法として機能は果たしていたと考える。
この患者の痛みの意味は、どこにあったのであろうか。
40歳くらいまで育てた息子が、もう独立しているとはいえ、自殺されて悲嘆にくれないわけがない。相当なショックが続いたものと予想される。そしてその重度の精神的不安定さを代償する意味として痛みが出てきたのではないかと考えた。痛みによって、その精神的苦痛から救われる。そのように患者の無意識が判断したのではないだろうか。
身体的な痛みに気を取られることにより、精神的な苦悩、不安が多少なりとも緩和されることはあると考える。無意識レベルの問題になり、また個々で異なってくることでもあろうが、自殺するほどの精神的な苦悩があるとすれば、身体の痛みのほうがまだ軽いということの方が多数なのではなかろうか。
さらには、その痛みの意味がそれだけではなかったのではないかと考えるに至った。それは、問診時の患者のmaternal affection1)に焦点を当てたことによる。先ほども触れたように、実は病気という意味合いでは、息子(弟)のほうが重症だったのではないかという点にはじまる。残された息子のほうもショックは相当のようであった。母親としては、すでに唯一となった家族に対してどうにかしなければならなかった。自身が痛みを訴えることで、僅かながらでも息子の注意を引くことが出来たのではなかったか。そこに母親としての役割を演じていた、無論無意識的にであると思うが。つまり、患者の痛みは、maternal affectionによりもたらされ、残された息子が立ち直るまでは消えないように働いていたのではないだろうか。
先に述べたように、10年後に痛みを題材とした市民講演会の際に、その患者に再会をした。にこやかに近づいて来られ、終始、また丁寧な配慮ある態度で話されていた。その後どうなったかを尋ねると、それでも痛みはまだ続いていますと言われたが、その表情はそれ程困っているというようでもなかった。自身の生き様として、ある意味生活の一部として機能しているような印象を受けた。
痛みは心的傷みの表れでもあり、悼み(追悼)儀式でもある。怒り、不安、怖れ、悲哀、傷つきなどの心的痛みは、実際の身体的痛みと転換される。そして身体的痛みに隠され、心的痛みを緩和、否認させる。さらに、関係性を支配、規定させていき、自らの孤独と空虚を埋めることになる。
補足
人と人との“つながり”によって、痛みに対応する。これは筆者がよく述べているスピリチュアルペインの対応に通じている。それは長い時間をかけて人が成し遂げた、他動物の脅威から生存競争で勝ち抜くための協力体制に基づく。人はつながることよって生き残ってきた。それは人の根底に根付いている。ゆえに人は“つながり”を失いかけたとき、恐怖を感じ、痛みを感じる。ただその恐怖や痛みは、無意識から発せられるので、意識的には所在が不定であり理解しづらい。そして人との触れ合い、つながることによってその症状は癒される。人が近くに居れば良いということではなく、“つながり”とは、そこに心の触れ合いが必要である。その人をどうにかしたいという気持ちが通じたとき、共に行動して行こうと連帯の気持ちが共鳴したときなどである。医師-患者関係でもスピリチュアルペインに対応するときに、その“つながり”は重要であるが、なかなか一般的とは言えない。ただ親子の場合など、それは一般的なことと言えるに近い。
この症例では、母と子の親子間での無意識的な“つながり”により、危機的状況の鎮火にあたっていたと考えられた。
Ⅱ.嗜癖としての痛み-慢性疼痛患者とのかかわり- 臨床心理士 西野敏夫
はじめに
筆者は麻酔科クリニックにて心理相談に従事している。ここには「痛い人々」がやってくる。繊維筋痛症をはじめ難治性の慢性疼痛を訴える患者が疼痛治療に併行して心理療法にまわされてくる。近年、医療においては、痛みに対する心理的アプローチ2) 3) 4)が求められており、ナラティブアプローチを中心に、催眠、認知行動療法、臨床動作法、筋弛緩法、支持的心理療法等、様々なアプローチがなされている。筆者もならティブアプローチを主として臨床動作法や筋弛緩法などを施行しているが、苦痛であるはずの痛みを手放せないでいる患者の状況はあたかも「痛み依存症」とでもいえそうな極めて嗜癖的傾向を示し、嗜癖という視点でのアプローチの有効性について述べる。
痛みについて
仮面うつ病や身体表現性疼痛をはじめ、多くの精神科疾患に慢性疼痛を含む身体症状はつきものであること、長時間痛みにさらされていると、疲弊、消耗しうつ状態を示すこと、二次的にアルコール、薬物依存症や他の問題をいくつも重複して抱えてしまうこと、さらに痛みが傷つき体験や怒りや攻撃性とも関連があることなどについては、すでによく知られている。
また、痛みは原発が身体要因によるものであったとしても、原発部位から拡散し、多様な修飾がなされてしまうことが少なくなく、その影響はBio-Social-Psycho-Spiritualに及ぶ。
痛みは、痛みへの感受性を過敏にし、その苦痛や不快さに比しなかなか手放せないという特性があり、自傷行為や食べ吐きやDV等の行為や関係において、不快、苦痛を伴う行為や関係や役割をなかなか手放せないのと同様に、治療を求めながらも苦悩や痛みを手放せず、痛いところに留まろうとしてしまう傾向が見受けられる。
嗜癖としての痛み
ペインクリニックに通ってくる患者のほとんどは、クリニック受診までに他科、他院、他所を回ってきていて、よくならなさから藁をもすがる思いで辿り着くことが多い。
しかし、このことが、やっと辿り着いた治療の場を失う不安から、痛みを助長してしまうことがある。つまり、治療を継続する必要性から痛みを手放せないように見受けられること、治療により痛みが和らぎはじめると、痛みを探し出そうとする傾向(痛み探索行動)がみられ、痛みが確認されると「やっぱり痛い、なかなか良くならない」と言いながら馴染んでいる痛い状況に戻ろうとしてしまうこと、痛みそのものと痛みを表現することによって、重大な「何か」が隠蔽され、痛みから解放されるとその重大な「何か」に直面する必要が出てくるため痛みを手放さないようにも見受けられる。
ペインクリニックに来院する患者の一部は、さながら痛みという酔いと安心を求めながら、痛みを取る治療に足しげく通うというパラドキシカルな状況にあるが、そこには痛むことによって、痛いと訴えることによって得られる承認や支援や免責があり、さらに痛いという訴えが何かの渇望表現手段となっている。それはパラドキシカルメッセージとして、メタ・コミュニケーションとして表現され、彼らが渇望しているものは痛みの除去ではなく別なところにあることが見えてくる。抱っこ、おっぱい、よしよしである。
このようにして痛みを訴える患者の行動特性は、極めて嗜癖的傾向を示し、痛みそのものも嗜癖的要素を持っていると言える。
アプローチの工夫5) 6) 7)
このように嗜癖的傾向を持つ痛みへのアプローチに、嗜癖という視点を取り入れることを持つことは多いに役立つと思われる。基本的には教育的アプローチが重要であるが、痛いという表現を無効化すべく逆説的介入により、「痛いから・・・出来ない」というコンテキストを「痛いけど、痛くても・・・出来る」というように書き換えてもらう。これにより患者の物語も、どれほど大変だったかではなく、どうやって生き延びてきたか、いかによくやってきたか、そして今も良くやっているかというものになって行く。逆説的課題の遂行により自己効力感を育て、それによって自尊心を育てて行くことにもつながるのだが、それらは副次効果で、一次的には患者の興味関心を逆説的課題の遂行達成へのシフトさせる介入の工夫がポイントとなる。
Ⅲ.自殺対策について
はじめに。
わが国では自殺者数が毎年3万人を越えていた(2012年は15年ぶりに3万人を下回った)。そこに至る原因は様々であろうが、うつ状態であることが大きな要因のひとつである。
ペインクリニックにおいて、うつ病の患者を診ることがしばしばある。体の痛みを訴える患者がうつ病が背景に隠れていることもよくある。痛みを継続すると,うつ病に罹病しやすくもなる。この点からもペインクリニック診療をする上で、うつ病や自殺を念頭におきながら痛み患者を診療することは重要ではないだろうか。
うつ病に対して、プライマリケアが重要であるとよく言われている。8)この場合のプライマリケアとは、精神的な症状のある患者に対し、専門である精神科を受診するまでの、一般診療科での診療のことである。名大精神科の尾崎先生によると9)「医療機関を受診するうつ病患者の80% 以上は精神科以外を受診し,プライマリケアを受診している全患者の約10% はうつ病に罹患しているとの報告がある」とある。海外では、軽症うつ病はプライマリケア医が診るべきと考える地域もあり、その方が結果も伴っているとされる。
わが国でも数年前からプライマリケア医を対象とした、うつ病診療の啓発セミナーや精神科医との連携に力が注がれている。うつ病に対するプライマリケア教育では、医師によるうつ病の診断、SSRI等による薬物治療、そして精神科医へのコンサルトなどが主であった。軽度うつ病治療において、より重要になってくるのは、患者との治療関係性であり、会話なのではないかとも思われる。
Lancet2010/12にうつ病対策について以下のように掲載されている10)。『うつ、不安障害などの「よくみられる精神障害(common mental disorders:CMD)」の症状を呈する患者をプライマリケアで治療する場合、訓練を受けた非医療者カウンセラーとの共同ケアによって病状の回復率が改善することが、ロンドン大学公衆衛生学・熱帯医学大学院のVikram Patel氏らがインドで実施した「MANAS」試験で示された。CMDは世界的な神経精神医学的疾病負担の主原因であり、自殺の増加や医療コストの増大を招き、経済的な生産性を低下させているという。』
ここでは、プライマリケアにおける、非医師によるカウンセリングの重要性が述べられている。現在のわが国の保険診療システムでは、なかなか同じような非医師によるカウンセリングを一般的に実施するのは難しいとも言える。ただ、今できることを考えれば、うつ症状などを訴える患者に対し、医師が診療の中でわずかな時間でも割いて、プライマリケアをすることであろう。
また、『プライマリケアにおけるCMDに対する共同介入の系統的レビューでは、1.スクリーニングのルーチンな実施、2.スタッフの専門的な技量、3.精神科専門医による監督によりアウトカムが改善する可能性が示唆されている。』という点も指摘されている。プライマリケア医師であっても、うつ病をはじめとした精神医学への関心や知識や、臨床心理学、心理的アプローチの知識や経験もある程度は必要と考える。
補足
自殺予防に留意する場合、自殺=うつ、という図式は適当ではない。自殺のハイリスク群はうつ病、という思い込みは横に置いておく方が良い。
むしろアルコール依存、ドラッグ、ギャンブル等のアディクション関連問題を抱えていたり、長期慢性疾患を抱えていたり、オーバードーズ、リストカット等の問題を抱えている患者、さらにはその家族にもっと配慮していくべきでもある。
Ⅳ.最後に
ドイツの哲学者ショウペンハウエルは、精神的苦痛と肉体的苦痛のどちらがより辛いかについて考えている11)。「肉体的に非常にひどく苦しんでいるときには、ほかの一切の心配などはどうでもよくなり、健康の快復が唯一の関心事となる。同じように、深刻な精神的苦悩は肉体的苦悩に対して我々を無感覚にする、我々は肉体的苦悩を軽蔑するのである。否、もしかして肉体的苦悩が優位をしめるようなことでもあるとしたら、それこそは一種心地好い気保養なのであり、精神的苦悩の一種の休止である。ほかならぬこういう事情が自殺を容易なものにしている。即ち並はずれて激烈な精神的苦悩に責めさいなまれている人の眼には、自殺と結びつけられている肉体的苦痛などは全くもののかずでもないのである。このことが特に顕著に見られるのは、純粋に病的な深刻な憂愁によって自殺へと駆られる人達の場合である。」
精神的苦痛とはある意味自殺をする以上に苦しい状況である。症例で述べられている身体的苦痛は、自身の精神的苦痛を包み隠し、どうにか平衡を保っている状態であると考えられる。さらには、無意識的なつながりにより、息子の精神的苦痛を緩衝させる意味も持っていたのだろう。そのように捉えた場合、このケースでは身体的な痛みが、うまく機能していたと言うことができる。
苦痛、苦悩はヒトが生きている中に満ちて存在している。苦痛、苦悩はより深く、それを意識させ考えさせるので、実感として残りやすいのに対し、不幸でもない状況では時間が徒に過ぎるだけで意識上に何も残らない。動物はヒトと異なり、未来を予期して考えず、現在だけを感じて生きている。ヒトは将来に対しての不安を抱く、老いて病になる苦しみ、さらにはその先の死を考えて恐怖する。そういった観点からしてみれば、ヒトは動物の中でもっとも不幸である。ただ、ヒトは苦しみの中で生きているが、その苦しみがもし無かったとしたら、定規がないと真っ直ぐ進めないように、欲望や傲慢に苛まれ道から外れることだろう。ある程度の心労や苦痛や困窮が必要であるとも言える。
希望とは何か。未来、将来における期待と喜び。しかしそれは同時に不安や憂慮を伴い、苦悩にもつながる。ヒトは動物と異なり、未来を予期し、将来を期待していくものなのである。
文献
1) Naito Yuji: A TENTATIVE PLAN TO THE STUDY OF INSTITUTIONAL CHILDREN: Investigation to Factors of Origination of Hospitalism:The Japanese journal of educational psychology 5(3), 32-40, 1958-03-25
2) Judith A. Turner, Joan M. Romano: Psychological and psychosocial evaluation. (John D. Loeser: Bonica’s management of pain, 3rd ed.). Philadelphia, Lippincott Williamals & Wilkins, 2001, 329-341
3) C. Richard Chapman, Judith A. Turner: Psychological aspects of pain. (John D. Loeser: Bonica’s management of pain, 3rd ed.). Philadelphia, Lippincott Williamals & Wilkins, 2001, 180-190
4) Eldon R. Tunks, Harold Merskey: Psychotherapy in the management of chronic pain. (John D. Loeser: Bonica’s management of pain, 3rd ed.). Philadelphia, Lippincott Williamals & Wilkins, 2001, 1789-1795
5) Wilbert E. Fordyce: Learned pain: Pain as behavior. (John D. Loeser: Bonica’s management of pain, 3rd ed.). Philadelphia, Lippincott Williamals & Wilkins, 2001, 478-482
6) Wilbert E. Fordyce: Operant or contingency therapies. (John D. Loeser: Bonica’s management of pain, 3rd ed.). Philadelphia, Lippincott Williamals & Wilkins, 2001, 1745-1750
7) Dennis C. Turk: A Cognitive-Behavioral Perspective on Treatment of Chronic Pain Patients. (Dennis C. Turk, Robert J. Gatchel: Psychological approaches to pain management: a practitioner’s handbook, 2nd ed.). New York, The Guilford Press, 2002, 138-158
8) Miki Osamu: The Clinical Feature of Depression with Psychosomatic Medicine in Primary Care:Japanese Journal of Psychosomatic Medicine 42(9), 585-591, 2002-09-01
9) 尾崎紀夫: プライマリケア医と精神科医の連携: 第129回日本医学会シンポジウム記録集 うつ病, 61-65, 2005
10) Patel V, Weiss HA, Chowdhary N, et al; Effectiveness of an intervention led by lay health counsellors for depressive and anxiety disorders in primary care in Goa, India (MANAS): a cluster randomised controlled trial: Lancet 2010 Dec 18;376(9758):2086-95.
11) ショウペンハウエル著 齊藤信治訳; 自殺について: 岩波文庫