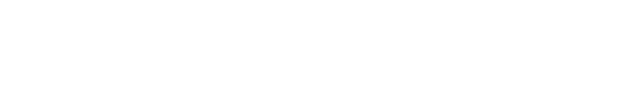痛みの心理的アプローチ
「痛み診療に対する心理的アプローチ」
要旨:痛みとは主観的なものであり、本質として心理的現象という側面もある。痛みの研究に心理学は不可欠であり、痛みの経験やその表現には、個々の心理的要素がその因果関係に重大な影響を及ぼしているといえる。慢性疼痛に対する心理的アプローチについて、精神分析的精神療法、認知行動療法など、その理論や目的、方法などを概説するとともに、動機付けやリラクゼーションについても言及する。
痛みに対する心理的アプローチについて
Ⅰ.はじめに。
痛みは組織損傷や炎症、末梢および中枢神経などが複雑に絡んで起こる現象であるが、痛みは個々が主観として捉えるものであることから、一側面として心理的現象であることには違いない。痛みの研究に心理学は不可欠であり、痛みの経験やその表現には、個々の心理的要素がその因果関係に重大な影響を及ぼしているといえる。一般的に、激しい痛みを体験すると意識が痛みに集中し、強い否定感情が表れ、痛みから逃れることばかり考える。
慢性疼痛は、重大な身体的・心理社会的機能障害をもたらし、患者をはじめ、その家族や医師、そして社会にとっても難しい問題となる。痛みや障害の原因となっている心理的要因、行動を特定する上で、包括的な心理的評価は役に立ち、治療の計画から実施まで必要不可欠な情報を提示し得る1)。
Ⅱ.痛みの心理的側面
脳には自己組織化能(self-organizing process)があり、環境変化に直面しても、長い時間をかけて、自分で定義し作り上げた秩序を維持しようと、また場合によっては再構築していこうとする。あらゆる組織には、自己組織化能が備わっており、他のものと区別し、独自の特徴を作り上げる。神経組織は生理学上、自己編成組織をもち、高度なレベルでは、記憶、集中、思考、感情などの認知機能の役割も担う。さらにレベルが高くなると、脳が意義や自意識、苦痛などを生じさせる。これらは受動的な機械的組織とは異なり、能動的な自己組織化である。
痛みとは複雑な経験であると同時に、生物体に損傷となり得るものを見抜くことができる自己組織化の一つであるともいえる。言い換えると、私たちは複雑な感覚刺激やその時の感情、記憶、過去の学習、また社会関係などから痛みの認識を独自に集め、整理している。同じ部位の同じ痛みであっても、人によって全く異なる感じ方をするのはそのためである。痛みの心理的側面は、どのようにその自己組織化がなされていくかの過程のことであると言える1)。
痛みに影響する認知要因は、知覚と思考の二つの過程に分けられる。知覚は通常、意図のない比較的分かりやすい過程だが、思考はより複雑で、普通は意図的に行われるものである。前者には注意力、描写、予想、記憶、定義づけなどが含まれ、後者には計画、決断、暗算、言語などが含まれる。
知覚・情緒レベルでは、痛みは不快なものであり、疲労や睡眠障害、認知記憶障害などを引き起こすことがある。睡眠障害があると正常な認知能力が退化したり、集中力散漫になりやすい。そして痛みにばかり注意をひきつけ、思考力を乱し、いずれは自己組織化を支配していく。それが慢性疼痛の場合では、痛みがあらゆる思考や行動のテーマとなってしまうこともある。痛みが記憶を歪ませることもあり、患者があえてネガティブな考えを選択して思い出すようになることもある。こうして痛みは患者の認知に支配的影響を及ぼすようになる。
痛みのために、自分のおかれている状況やストレス因子を客観的に把握する能力が妨げられ、悪循環ができる。痛みのことばかりにとりつかれ、うつ状態や睡眠障害を引き起こし、次第に社会活動や職業活動などから退くようになる。こうした生活変化がさらに痛みの対処手段を減らしていくことにつながり、痛みへの集中がますます強化される。このような場合、患者が通常の活動に復帰し、痛みに適応できる思考力やストレス対処法を身につけられるよう促す多角的なアプローチが必要になる。
痛みの問題は人によって大きく異なり、痛みの捉え方、対処法、付き合い方もさまざまである。痛みの対処法は個人の身体的・社会心理的適応力に深く関係しており、特に物事をポジティブに捉えるかネガティブに捉えるかどうかで痛みに対する自己支配力が大きく変わる2)。
Ⅲ.心理的評価
心理的評価によって疼痛原因の特定はできない。実際に検査で身体的損傷が認められなくても、痛みが単に心因性によるとも断言できない。医師に病名を「心因性疼痛」と分類されることで、中には怒りや防御反応をみせる患者もいる。それによって医師-患者関係が悪化し、良好な治療関係を構築することが困難になり得る。また、患者にとって心理的評価をされることは、痛みが単なる思い込みである、さらには精神障害の疑いと診断されていると感じやすいものである。従って、心理的評価をする意義など患者に伝える際は、言葉を慎重に選び、協力的になってもらえるよう促す。そのためには心理的評価の前に、患者に十分な心構えができていることが前提である。痛みが心因的なものであるかを確かめるためではなく、痛みを悪化させやすい他の問題やストレス因子を特定し、より最適な治療法を見つけ出すために評価することを伝えておくべきである。
~心理的評価に含まれる内容~
- 痛みの病歴と現在の症状
- これまでの治療法
- 薬物・アルコール依存
- 行動分析
- 行動変化
- 社会的関係と強化因子
- 防衛行動
- 職業評価
- 補償・訴訟
- 社会的経歴
- ストレス
- 心理的障害
Ⅳ.痛み行動という観点から
痛みというのは“モノ”というより、concept(概念)であり、これにより痛むことや苦しむということがはじめて理解できる。もし痛みが、物理的な侵害刺激→反応だけで成り立つとしたら、神経解剖学だけで十分解釈でき、学習や認知では解釈できない。侵害刺激があると、主観的な不快感やなんらかの痛み行動が表れるものである。こうして刺激に対する反応が出るが、この反応からその人が痛みと認識したものを経験していることが初めて分かる。反応を持続すること、あるいは、抑制することを学習することで、状況に合わせ反応をコントロールできるようになる。
行動は、物理的刺激だけではなく、過去の学習や経験から影響を受ける。私たちは日頃、暗黙の了解で決まりきった概念に左右されながら、考えたり行動することをあまり意識していないが、この概念モデルのおかげで、私たちは目の前にある出来事を瞬時に理解できる。痛みの問題において、痛み行動は必ず出てくるものであり、それは環境の影響を受けやすく、社会フィードバックによって変化していく。
痛みにおける医学的モデルと心理社会モデルには違いがあり、医学的モデルでは診断上、何が痛みを起こしているのか、侵害刺激を探し当てることに重点を置いているのに対し、心理社会モデルでは、どのような複雑な原因があって痛み行動が誘発されたかが重要視される。片方のモデルだけで痛み行動を説明することは難しく、どんな場合でも両方のモデルが関わる2)。
痛み治療における第一目標は、侵害刺激を減らす、もしくはなくすことであり、症状ではなく、その原因を治療していく。次に治療の焦点は、痛み行動を変えていくことに当てられる。最終的には、痛みの原因も症状も治療していくことになり、根本的な医学治療と認知行動学習の両方のアプローチが必要となる。
痛みが苦悩なのか、それ以外の理由で苦悩なのかは、混同されやすい。痛みを経験するとき、まず侵害刺激を感知するが、その段階では、その刺激をどう解釈するかが問題となる。同時に、その状況で何が起きそうか、どんな結果が出てきそうか予測される。人は、今にも起こりそうな破壊状態を感知した時、苦悩が生じ、破壊状態が終わるまで苦悩は続く。痛みも同じで、激しい痛みや体に何か異変があると苦悩を感じやすくなる。侵害刺激と同様に、苦悩は痛み行動を生じさせ、ゆえに将来がはっきりしないと痛み行動が強化されることもある。
痛み行動はオペラント学習されやすいため、もともとは刺激に反応して生じたとしても、刺激が消えたり症状が完治した後にも、痛み行動だけが痛みの症状とは無関係に表れ、長期化することがある。つまり、行動が学習された結果、刺激が実際になくても痛み行動だけが繰り返される。侵害刺激が長期化する結果、防衛行動や休息行動が促される傾向もある。強化因子となり得るのは患者の誤った認識や痛み行動に見合った環境によるものが大きい。
オペラント行動療法が実際どのようにして痛み行動変容に応用されるのか見ていく。次の三つの主義が連結してオペラント行動療法の基礎を形成している4)。
①「行動」とはある特定の社会的場面で刺激によって引き出される行動パターンや動きを指し、日常一般的な行動、思想、感情とは異なる。
②行動は結果に左右されやすく、行動の結果が肯定的であるほどその行動が起きる頻度が高くなる。
③行動の強化はその人の過去の経験によって決定される。
行動変容には、具体的にどの行動が極端に多く見られ、どの行動があまり見られず、そしてどの行動が全く見られないのか、行動の特性を特定することが必要となる。ある行動が肯定的な結果につながると、その行動がまた頻繁に生じるよう方向づけられ、反対に否定的な結果が付随すると、その行動はあまり強化されない。強化因子となる事柄も人によって異なり、その人の過去の経験が重要な決定要素となる。強化因子の特定には、どの行動が頻繁に見られるか観察することが重要である。
治療する側は、患者の治療への意欲的態度には肯定的に反応し、適切な行動を促進するよう努める。ただ褒め過ぎたりすることは逆効果になることがあり、注意が必要となる。患者の痛み行動がみられたときは、無視するのではなく、アイコンタクトをとるなどして控えめな反応を示す。
Ⅴ.慢性疼痛における認知行動療法(cognitive behavioral therapy; CBT)
慢性疼痛を完治させることはできない。このため、治療は慢性疼痛に関連する認知的、情動的、行動的側面など全てを扱うべきである。身体上の治療だけでは不十分である。また、患者自身が長期に渡って症状を管理していかなければならず、その方法を患者が学ぶ必要がある。認知-行動(C-B)アプローチはそうした疼痛管理のためのものである。
慢性疼痛へのCBTの適用原理は、痛みまたは痛みに影響する要因に対してどのように認知し行動するべきかを学習することで、自分自身で痛みを適切にコントロールできる能力を獲得することにある。不適応行動を減らし、適応行動を増加させることは、疼痛の軽減につながると考えられる4) 5) 6) 7)。(表1)
CBTにおいて、下項目のことが必要となる。
- 患者には情報を論理的に提示し、口頭だけでなく書面でも治療の詳細を説明する。
- 患者ひとりひとりに合わせた治療計画をつくり、患者が困惑することのないよう情報は少しずつ開示していく。
- 治療が終わったらどうしたいか聞くことで患者の理解を確かめ、必要に応じて宿題を課すことや患者の家族にも治療に参加してもらうことも考慮する。
- 患者にとって障害になっているものを把握し、それを克服できるよう努め、患者の理解がついてきているかを随時確認する。
CBTには幾つかの種類があるが、ここでは主要なものを紹介する。
A. 認知再構成法
ネガティブな状態に直結しやすい否定的な考え方をしていることを患者自身が客観的に見極め、それを変容していけるよう促し、それに代わるもっと前向きで現実的な別の考え方を見出せるよう導く方法である。この技法を獲得するのに多くの治療セッションが必要になるが、その中で患者に強い痛みやストレスを感じた時に、その時の気持ちなどを記録してもらい、次のセッションで例として取り上げることは非常に有効である。例えば患者にできること、できないことをリストアップしてもらい、できない事柄として挙げられた活動がどのくらい患者にとって重要なことか、その内いくつかは痛みがあっても、他の方法でできないかなど話し合う手法である。回を重ねていくと、患者のネガティブな考え方のもとにある何かが見えてくるはずである。ネガティブな感情は生活をしていればあって当然のものであるが、それを取り除くことが目的ではなく、その度合いを減らしていくことが重要となる。
B. スキル対処法
特にリラクゼーションや自己主張訓練などの技法を適用して、痛みやストレスに対処できる技法のレパートリーを増やしていく治療法である。医師が幾つかの方法を提案し患者に選択させることも効果的で、筋肉の緊張をほぐしたり深呼吸をしたり、治療の中だけでなく自宅でも練習をして効果がみられるのに数週間は必要となる。
C. グループ療法
ひとりの医師で一度に多くの患者さまを治療できる点や、同じような状況にある他の患者とふれ合い励まし合うことで、得るものが大きい点が最大のメリットである。
Ⅵ.CBTの効果因子について
CBTは様々な慢性疼痛に効果があることが証明されている。その効果の要因を特定することで理論モデルがより精密となり、治療が効果的かつ効率的になるであろう。
①自己効力感self-efficacy
②痛みが行動不能をもたらすという捉え方;disability(pain behavior)
③痛みが障害をもたらすという捉え方;harm(pain behavior)
④痛みを制御できるという捉え方;control (pain behavior)
⑤破滅的な考え方(catastrophize)
⑥痛みの思い返し(catastrophize)
⑦リラクセーション(coping)
以上7項目を評価したところ、control(pain behavior)が最も効果要因として高く、他要因との連動があり、一方self-efficacyだけは独立の因子であった。CBTではcatastrophize、disability、harm、controlは治療要素として重要であり、また自己効力は別の効果をもたらすと考えられた。
予測因子として①年齢・性別・人種・教育歴・疼痛期間、②疼痛部位の数、③抑うつ度、④神経症傾向と開放性、⑤身体症状、⑥ストレス度、⑦catastrophizeにつき評価され、身体症状、抑うつ度、疼痛部位の数、catastrophize、ストレス度が活動障害の結果に有意に関連しており、そのような患者に対しての対策が望まれる。神経症、開放性には相関がなく、どのような性質の患者にもCBTが効果をもたらす可能性が示された8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)。
Ⅶ.慢性疼痛管理における精神分析的精神療法
精神療法に関する研究論文は数多く存在するが、精神療法の結果を測りその有効性を判断することは困難であるため、多くの心理療法学派を悩ます種になっている。精神療法の有効性を評価することが難しい原因として、
1(CBTの場合を除いて)結果を表す測定値が治療法にもともと組み込まれていない。
2治療における人と人との関係性が重要であり、容易に数量化できるものではない。
3治療結果には通常、自己認識の向上、理解力など主観的変数を伴うため測定することは難しく、ましてや他の患者や治療法と比較することは困難である。
4支持的療法、精神力動的療法、来談者中心療法、対人療法、家族療法、グループ療法を含む治療法では効果があるか否かは患者と治療者の関係の形成と発展次第であることが多く、治療コースは患者によって異なり、心理療法に十分な科学的構図をつくることは難しいなどの点が挙げられる15) 16) 17) 18)。
次に慢性疼痛治療に使われる4大精神療法を紹介する。
- 支持的精神療法
心理療法の中でももっとも重要視され広く知られている療法である。患者が「自分の話を聞いてくれた」、「自分のために時間を割いてくれた」、と人から共感を得ることができる。現実や可能性、決断をすることに重要性をおき、たとえ悪状況下にあっても患者は問題と向き合い、自分の力を信じ前向きになるべきという考え方が基になっている。
実際に治療者が考慮するべき事例として、
- 現在抱えている問題が何で、その原因は何だと患者は認識しているか
- その問題を対処したり避けたりする為に、現在どんなことをしているか
- 今患者の強みや問題解決能力、頼りになるもの(家族・仕事・社会生活など)は何か
- 精神的安定を取り戻すために何が変わればいいか
- 問題が生じた時に患者は以前どんな方法で乗り越えてきたか
- 治療セッションにはどのくらいの頻度と期間が必要でどう完結させるか
- どうしたら治療者に頼る状態から自力で対処できるように変わっていけるか
などが挙げられる。
- 洞察的精神療法
支持的療法と同様、患者とセラピストとの関係性が重要になってくるが、洞察的精神療法はより複雑な心理分析法の概念に基づいている。関係から得た洞察を通し自分の考えや価値観を再構築していく方針で、患者の内なる意識的・無意識的考えや葛藤、防衛などが行動を左右しているという考えに基づいている。
- 衝動や分別、自己認識などの精神のある特定の部分は洞察を得ることで変化しやすい
- 個人の考え方、信念、行動などのパターンは成長の過程の経験から身についたものであり、これらのパターンが土台となり性格が形成される
- 問題が生じたときの現在の対処法は過去の対人関係で学んだ問題解決を反映している
これらが洞察的精神療法の中心的概念になっている。
洞察的精神療法だけでは疼痛患者治療に適するとは言えず、他の疼痛療法と組み合わせることで効果を発揮しやすいといわれている。特に心理的苦痛に悩んでいる場合、自分の衝動や感情に混乱している場合、治療過程で抵抗をあらわにしている場合などに適している。
③ 家族療法
慢性疼痛によって苦痛を強いられるのは患者だけではない。家族も巻き込まれやすく、疼痛治療プログラムでは当初より家族メンバーの参加が選択されることがある。家庭内の衝突を掘り起こして見つけ出すのではなく、家族の方々が満足のいく方法でコミュニケーションをとり、最終的には問題解決ができるよう手助けすることにある。家族療法が適するかどうかについては、以下の項目が指標となる。
- 病気が家族機能を乱すものになっている
- 家族が患者の問題の原因であり、長引かせている要因であると考えられる
- 多種多様な問題で家族が困惑している
- 患者が子供である
- 家族が家族療法アプローチに十分興味をもっている
- 疼痛治療のために家族のメンバーをセッションへ結集できる
過去の経験を集めて現在を理解しようとする力動学的療法とは異なり、家族療法は「現在」に焦点を当て、家族全体を患者とみなしてコミュニケーションに重点をおく。
④グループ療法
グループ療法の強みは同時に何人かの患者を一度に治療でき時間の節約になるだけでなく、患者同士がお互いに刺激を受けながら学べることもメリットである。グループという形が教育面もカバーでき、疼痛管理の正しい知識を得て、仲間の経験談を共有して問題対処法を獲得し、適切な自己主張やコミュニケーション能力を上げることができるようになる。
Ⅷ.その他、Relaxation & Imagery 療法(以下R&I療法)
リラクゼーションは、理論的には痛みから気を紛らわし、筋肉の緊張を緩和するために用いられる。イメージ療法はイメージに気が集中することで痛みへの認識を妨げ、治療後は疼痛緩和状態が持続する傾向にある。R&I療法は慢性疼痛、癌性疼痛、リウマチ関節炎、また出産時陣痛に効果的であるというデータがある。頭痛や顎関節症にはリラクゼーション療法単独で、あるいはイメージ療法との併用で効果が出ている19)。
- 深呼吸法は特に急性疼痛に最適で、出産時によく見られるような腹式呼吸法などがある。
- Progressive muscle relaxation(PMR)はもっともよく使われるリラクセーション療法のひとつで、心身にリラックスした状態を覚えさせることが目的である。緊張-弛緩といった身体動作を通じて得られる筋感覚が段階的にわかるようになり、体のどこかに不必要な緊張があったりするとそれにもいち早く気づくことができるようになる。
- 自律訓練療法は体の各部位に重たさや温かさを感じることをイメージするもので、自然治癒力を高め、心身共にリラックスさせ、ストレス緩和、自律神経のバランス回復効果が期待できる。
- イメージ療法とリラクセーション療法を併用することで、疼痛緩和療法としての効果が非常に高まる。あるイメージを強く潜在意識に焼き付けることで、潜在意識はそのイメージを実現させようと働き始める。自分がゆっくりとくつろげる場所をイメージしているだけで体の緊張がほぐれ、心身ともにリラックス状態になる。どんな場所であれ、不快な状態になってもこのイメージ療法が応用できるようになると、不快感や痛みをセルフコントロールできるようになる。
- バイオフィードバック療法は脳波計や筋電計、心拍数などを用いて身体の状態を視覚的に確認していく治療法である20)。
- 瞑想療法はあるフレーズや単語を繰り返し自分に言い聞かせる方法(relaxation response)と、痛みの感覚を変容させてしまうアプローチがある。後者は呼吸法を多用した心理療法で、現在の自己の心に起きている事を自覚しながら目前の大切なことに意識を集中し続ける動的な心のスキルで慢性疼痛患者の間で効果がみられている。
Ⅸ.疼痛患者の行動変容に対する動機づけについて
慢性疼痛治療は通常の治療に比べ、患者が積極的に治療に参加していくことが求められる。一通り治療が終わると、薬物治療の増減を調節されたり、適度な運動を引き続き行うよう勧められたり、仕事復帰に向けてのプランやリラクゼーションなどの痛み対処法についての助言を受ける。慢性疼痛治療では、多くは患者の努力次第で決まってくるため(自己管理)、患者の動機づけが重要な役割をもっている。
医師と患者が一連の治療計画に同意し、患者もその治療に積極的に参加していく意欲を見せている場合は問題ないが、今後どのような治療を行っていきたいかの医師と患者の考え方に相違がある時などは、動機づけが課題となる。その場合、医師の選択として、その患者の治療を辞退し、他の専門医を紹介することもある。別の選択肢として、患者が抵抗してもその治療を勧め続けることもある。また三つ目の選択肢として、医師が治療を始める前に患者の動機づけに時間を割き、それから治療を進めていく方法がある21)。
- 動機づけに時間を費やすことで、患者に行動変化を導くことができると考えること。
その治療を医師が勧める際の状況や雰囲気にかかっているともいえる。
- 行動変容への動機づけを促す上で医師の役割が重要であること。
患者ひとりひとりの問題や状況に合わせ、患者と一緒に治療計画を作り上げていくことが望ましい。
- 行動変容は段階的なものであることを理解すること。
文献
1) C. Richard Chapman, Judith A. Turner: Psychological aspects of pain. (John D. Loeser: Bonica’s management of pain, 3rd ed.). Philadelphia, Lippincott Williamals & Wilkins, 2001, 180-190
2) Wilbert E. Fordyce: Learned pain: Pain as behavior. (John D. Loeser: Bonica’s management of pain, 3rd ed.). Philadelphia, Lippincott Williamals & Wilkins, 2001, 478-482
3) Judith A. Turner, Joan M. Romano: Psychological and psychosocial evaluation. (John D. Loeser: Bonica’s management of pain, 3rd ed.). Philadelphia, Lippincott Williamals & Wilkins, 2001, 329-341
4) Wilbert E. Fordyce: Operant or contingency therapies. (John D. Loeser: Bonica’s management of pain, 3rd ed.). Philadelphia, Lippincott Williamals & Wilkins, 2001, 1745-1750
5) Judith A. Turner, Joan M. Romano: Cognitive-behavioral therapy for chronic pain. (John D. Loeser: Bonica’s management of pain, 3rd ed.). Philadelphia, Lippincott Williamals & Wilkins, 2001, 1751-1758
6) Dennis C. Turk: A Cognitive-Behavioral Perspective on Treatment of Chronic Pain Patients. (Dennis C. Turk, Robert J. Gatchel: Psychological approaches to pain management: a practitioner’s handbook, 2nd ed.). New York, The Guilford Press, 2002, 138-158
7) 西川泰夫:認知行動科学.東京,放送大学教育振興会,2002
8) Judith A. Turner, Susan Holtzman, Lloyd Mancl: Mediators, moderators, and predictors of therapeutic change in cognitive-behavioral therapy for chronic pain. Pain 127: 276-286, 2007
9) Jensen MP, Turner JA, Romano JM, et al: Relationship of pain-specific beliefs to chronic pain adjustment. Pain 57: 301-309, 1989
10) Keefe FJ, Caldwell DS, Queen KT, et al: Pain coping strategies in osteoarthritis patients. J Consult Clin Psychol 55: 208-212, 1987
11) Morley S, Eccleston C, Williams A.: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials of cognitive behavior therapy and behavior therapy for chronic pain in adults, excluding headache. Pain 80: 1-13, 1999
12) Sullivan MJL, Bishop SR, Pivik J.: The pain catastrophizing scale: development and validation. Psychol Assess 7: 524-532, 1995
13) Turner JA, Dworkin SF, Mancl L. et al: The roles of beliefs, catastrophizing, and coping in the functioning of patients with temporomandibular disorders. Pain 92: 41-51, 2001
14) Brister H, Turner JA, Aaron LA, et al: Self-efficacy is associated with pain, functioning, and coping among patients with chronic temporomandibular disorder pain. J Orofac Pain 20: 115-124, 2006
15) Eldon R. Tunks, Harold Merskey: Psychotherapy in the management of chronic pain. (John D. Loeser: Bonica’s management of pain, 3rd ed.). Philadelphia, Lippincott Williamals & Wilkins, 2001, 1789-1795
16) Stephen C. Basler, Roy C. Grzesiak, Robert H. Dworkin: Integrating relational psychodynamic and action-oriented psychotherapies: treating pain and suffering. (Dennis C. Turk, Robert J. Gatchel: Psychological approaches to pain management: a practitioner’s handbook, 2nd ed.). New York, The Guilford Press, 2002, 94-127
17) 大場登:臨床心理面接特論.東京,放送大学教育振興会,2002
18) 橘玲子,齋藤高雅:臨床心理学特論.東京,放送大学教育振興会,2002
19) Karen L. Syrjala: Relaxation and imagery techniques. (John D. Loeser: Bonica’s management of pain, 3rd ed.). Philadelphia, Lippincott Williamals & Wilkins, 2001, 1779-1788
20) John G. Arena, Edward B. Blanchard: Biofeedback therapy for chronic pain. (John D. Loeser: Bonica’s management of pain, 3rd ed.). Philadelphia, Lippincott Williamals & Wilkins, 2001, 1759-1767
21) Mark P. Jensen: Motivating the pain patient for behavioral change. (John D. Loeser: Bonica’s management of pain, 3rd ed.). Philadelphia, Lippincott Williamals & Wilkins, 2001, 1796-1804