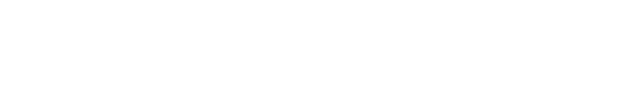非がん性のspiritual pain、social painについて
1.はじめに
緩和医療、緩和ケアでは、痛みをトータルペインとして取り組むことが一般的である。Spiritual pain、Social painについての定義もされており(図1)、がん患者の痛みを治療する上で考慮されるべき項目である。
心理的痛み:Psychological Painという用語についてであるが、狭義においては不安や緊張、うつ状態に関連する痛みを表し、いわゆる意識観念上の日常に起こる出来事に関連した思考変化によるものである。しかし広義的には、心理的痛みを身体的痛み以外の精神的(mental)理由すべてに関連する痛みとして扱われることもあり、なかなか誤解を生じやすい部分でもある。Spiritual pain(Social Painも同様)のspiritualとは、無意識領域に関する状態を表しており、思考により認知できる不安やうつ状態などの精神的状況に伴った痛みとは明らかに異なると考える。
2.がん患者のスピリチュアルペインについて
WHO専門家委員会の報告書には、『スピリチュアルとは、人間として生きることに関連した体験的一側面であり、身体感覚的な現象を超越して得た体験を表す言葉である。多くの人々にとって”生きていること”がもつスピリチュアルな側面には宗数的な因子が含まれているが、スピリチュアルは”宗教的”と同じ意味ではない。スピリチュアルな因子は身体的、心理的、社会的因子を包含した人間の“生”の全体像を構成する一因子とみることができ、生きている意味や目的についての関心や懸念と関わっている場合が多い。特に人生の終末に近づいた人にとっては、自らを許すこと、他の人々との和解、価値の確認等と関連していることが多い』となっている。
末期がん患者が痛みを訴える場面で、身体的因子として痛みの原因が分からないと、それはスピリチュアルペインではないかと疑うことを臨床の場ではよくある。他方、スピリチュアルペインは、イメージの沸き難い概念でもある。無価値感や孤独感、無意味感など(表1)を患者が口にしているのを見聞きすることが、患者のスピリチュアルペインを捉え対応する際に臨床的に役立つとされる1)。
がん患者のスピリチュアルペインに対して、医療者側はただ傾聴すれば患者は救われるといった単純なことでもない。「共感的態度」「死後の世界のイメ-ジを語り合う」「希望の共有」「ユーモアからくる慰め」「愛を感じさせる言動」などが奨められており、臨床上それらが有効であると感じている。また患者との間に、無意識的な心と心で伝達される、単なる言葉ではない何かが必要とされるとも考えられ、日頃から死について考え巡らしセンスを養っておくことや、生の意味や目的、存在の価値について自然と伝わるように考えておくことが必要であるとも言える。
3.Social pain について
Social painは、緩和医療、緩和ケアの中では、仕事上の問題、経済上の問題、家庭内の問題、人間関係、遺産相続問題などが関連すると一般的には定義されている。つまり社会活動に関係したものについてということになる。
「社会的痛みは、友人や恋人、家族、仲間のような望ましい関係性から排斥されたり、低く評価されたりしたとの知覚に対するネガティブな感情反応である(Macdonald & Leary, 2005)。ここでの排斥とは、拒絶や死別、強制分離などを含む。また低評価とは、恋人になりたいのに友人としてしかみてもらえないといったような、望ましい関係性よりも低く評価された状態を指す(Leary & Springer, 2001)。こういった低評価も、排斥の可能性を増大させる信号として働くので嫌悪として経験されることが指摘されている(Macdonald & Leary, 2005)。」というようなsocial painついての意見もある
このような定義であると、それは原因論であって、結果としてのpain(social)がpsychological painとどのように異なるか明確ではない。その場合、ただSocial painが人間関係などいわゆる社会活動上のトラブルが原因で、psychologicalな痛みが出現していると差異がなくなる。つまりsocial painとしての意味であり独自性が失われるのではないだろうか。
4.非がん性の慢性疼痛患者におけるspiritual pain、social painについて
非がん性の慢性疼痛を訴える患者において、身体的な痛みだけを苦しんでいるようには見えないことがよくある。さらには、心理的な痛みの範疇と考えても、うつ病や不安障害など精神科領域の観点からでもなかなか説明できないようなことも多く、抗うつ薬や抗不安薬が痛みの軽減に直結しないこともしばしばある。その際に、がん性疼痛と同様に非がん性慢性疼痛に対しても「トータルペイン」として対応していくことが何かしらの役に立つのではないだろうかと思う。がん患者では、『死』という直に迫ってくると予期される直接的な結果に対し、無意識的哲学的な恐怖に苦しむ。非癌性の慢性疼痛患者では、直接『死』が苦しみになるというより、『生きる』という局面でさまざまに根源的な苦しみがあり、また、間接的には将来における『死』も、がん患者と同様に恐怖につながる。
以上のことを踏まえ、非癌性慢性疼痛患者では生という面からspiritual pain、social painを抱えているのではないかと思われた。それにつき定義付けが可能となれば、今後の慢性疼痛患者に対する診療の方向性も変わるのではないかと考えた次第である。
4-1. Spiritual pain
A. ヒトの進化の過程
今から20万年前に、人類の直接の祖であるホモサピエンスがアフリカで誕生した。それを遥かに遡ること700万年前には、サルから人類の祖先が分岐したとされ、それが人類誕生の起源とされている。サルと人類の祖先が進化の上で分かれた際の大きな相違点がある。サルはそれまで安全な木の上で生活をしていたのに対し、人類の祖先は木の上の安全な生活を捨て地上に降りたことである。そこから生活の場が、森から草原に移った。草原では安全な生活が確保できず、捕食動物から逃げ隠れすることもできない。そこで、人類の祖先は今までになかった互いに協力するといった捕食動物から生き残る選択をすることになる。また二足歩行に伴う骨盤の形態に関連した出産形式や、生後の自立までの期間が長いことによる世代を超えた周囲の子育て支援等も、生き残るために必要であった「協力し合うというシステム」を作りあげ、受け継がれることに関係する。
協力性は、ヒト科の非常に基本的な特徴である。チンパンジーと比べ、ヒトは一人では生きられない。何らかの形で他人に依存しなければならず、助け合いがヒトの社会の基盤ともいえる。チンパンジーは自ら進んで利他行動をしない。助けるが、助け合わない。ゆえにお礼もない。それはお礼しないことが前提となっているからである。
B. ホスピタリズム
ホスピタリズム(hospitalism)という概念がある。特別な事情で母親から離れて乳児院・孤児院・児童養護施設で育てられた子どもに発症しやすい発育障害・情緒障害・パーソナリティ問題のことである。児童養護施設など栄養状態や衛生状況には問題はないが、母性的養育が欠如すると、子どもの発育上・健康上の問題が発生する。養護施設で育てられた乳幼児は、母親との愛着(アタッチメント)を形成する機会がないことが多く、自己対象(重要な特定の他者)を得られないことで、他者への基本的信頼感を獲得できずに強い孤独感と無力感を感じるようになる。ホスピタリズムの原因は『母性的養育の欠如』にあり、子どもに不安感・孤独感・無価値感を与えて『生きる意欲・母子関係の安心』を奪ってしまうのである。
ホスピタリズムでは、乳幼児の死亡率と病気の発症率が高くなり、免疫能・抵抗力の低下によって一度かかった病気の回復が遅れるという特徴がある。施設に預けられた子どもは、自分の泣き声や訴えに迅速に職員(保育士・福祉士)が反応してくれないと、顔の表情や感情表現が乏しくなり元気がなくなっていくが、その状態が長期間にわたって続くと周囲の刺激に対する無関心や物事に対する無気力・無感動といったパーソナリティ特性の偏りが生まれてくる。周囲の養育者の愛情や反応が不足し過ぎると、乳幼児の行動の自発性や他者への共感性が低下してくるという問題があり、予防するためには乳幼児ひとりひとりに十分な愛情・関心・配慮をして上げることが必要となる。
- Spiritual painとは
ヒトの進化の過程からも、ホスピタリズムからも見て分かるように、ヒトの中には長い期間に渡り染み込んだ、一人では生きて行けないという特徴が身体的にも、無意識レベルにもあるのではないだろうか。ヒトはヒトとのつながりが必要である。そしてヒトが、そのヒトとのつながりを断たれるとき、もしくは断たれる可能性があるとき、人間として根源的に苦しみ、痛みを感じるのであろう。その苦悩は、末期がん患者の死が近くなるにつれ、この現実世界での人とのつながりが断たれようとしている時など理解しやすい。ただ、非がん性の慢性疼痛患者においても、人との触れ合いの欠如に関連した苦悩が、同様に起こり得ると考えても間違いはないだろう。例えば、身寄りなく周囲と関わりもなく、通院困難で一人暮らしをしている慢性疼痛患者などは典型的である。
乳幼児のように高次機能が未発達で、非言語的世界に生きている時期に、言葉ではないアタッチメントが不足することにより、生命に危機がもたらされている。それはヒト個体に元より備わったものであり、またそれだけでなく成長してからも生存していくために必要なものなのではなかろうか。ヒトはアタッチメントが得られないと、もしくは得られない予期があるとき、その為に苦悩を伴うことになるのだろう。
そのような観点から、スピリチュアルペインとは死に際してだけでなく、死と直接関係なく生活している段階においても、人と触れ合いがないことに関連した、生体として無意識レベルでの苦悩からも起こりうると考える。それが非がん性慢性疼痛患者におけるスピリチュアルペインと考える。
4-2. Social pain
- 組織(集団)と痛み
ヒトは社会性のある生き物である。前述したように、集団(組織)を組むことは、森林から平地へ住み場所を移して以降、肉体的に周囲の動物より弱いヒトの生存していく術であった。それは利点でもあるが、それによる弊害も生じることになる。
ヒトの社会性の中で重要なものの一つは、前述の協力である。他の個体(ヒト)を思いやる気持ち、分かち合い助け合う精神なども含まれる。それらが集団の基本的事項であることは考えやすい。各個人では困難なことであっても、目的を同一として協力していけば遂行することが可能なこともある。何かに困っているヒトがいれば、助けたり、分かち合ったりする。逆に自分が困っていれば、分けてもらったり助けてもらったりする。
一方、そのように集団(組織)に属することは、周りのヒトとの関係性を保たなければならないという側面も併せ持っている。集団を形成するには、利己的な行動は慎まなければならない。組織を維持するために、他との関係性に注意を常に払うことも必要である。そこには必然とルールや規制といったものが存在することになる。それを破れば罰が与えられることになる。ヒトの集団化が際立つようになった頃より、規律違反の罰として、ヒトはヒトに対して体を傷つける、果ては殺してしまうなどの痛みを与える行為をするようになった。ヒトはより社会的な動物なので、共感能力が研ぎ澄まされ、かつ、非協力的な対象を排除するような仕組み(処罰を快感とさえ感じる)が備わっているという面も指摘されている。
この規律違反に対する懲罰である痛みこそ、social painの根源ではないだろうか。つまり、ヒトは規律違反に対する懲罰である痛みを内在していて受け継がれているということである。長く受け継がれてきた遺伝としての身体の中や、教示として組み込まれた環境や社会の中に、無意識レベルということになるが組織(集団)としての痛みが存在しているのではないだろうか。
一族や組織を守るため存続させるため、また共同で暮らすためのアイデンティティが失われないようにするために行われる社会的制裁と、集団で協力することは二律背反的な行為でもある。social painと、spiritual painとは、相反するウラとオモテのような関係なのである。他人を羨む、ねたむ、恥じる、ひがむ、のろう、コンプレックスを持つことはチンパンジーにもみられることであるが、ヒトには多く認められ、他者との比較をよくすると言われている。これはヒトの共感能力に関係するもので良い面にも悪い面にもなり得るが、協力と対立の二面性を表すことにも関わるのだろう。
B. Social painとは
集団(組織)と規律は現在においても、どの社会にも見られる。むしろ現在に近づくにつれ、集団が大きくなり、規律や規制は細かく、かつ厳しくなっている。それに伴い受ける精神的ストレスもますます多大になっている。現代社会では、機械化、コンピュータ化、IC化が進み、些細なミスや多少の緩みも許されないような生活が強いられる。産業革命後の技術革新が続いた結果として糸が張り巡らされたような、何をするにも繊細さが要求される環境と相まって、大きくなった組織(集団)が現代人の社会的なストレスを増大させ、その結果として痛み、苦しみをもたらすことになる。周囲との関わりなく一人で生きていけば、このような痛みや苦しみはないだろう。しかしそれはヒトの進化の過程では存在しなかった。
組織の構成員である個々人はさまざまな制約を受け、かつ逃げられない状況となっている。そこには一人では生きて行けないという進化の過程、もしくは一人では生かせないようにしている組織集団主義もある。その組織、集団にいる個人は、社会のルールから集団組織の規律、集団組織による対人関係など、さまざまな制約を受けストレスを多かれ少なかれ受けることになる。そのストレスが処理不能なほど多大になると身体症状や精神症状として現れることになる。過去から受け継がれてきた組織、集団から逃れられない苦しみ=social painがその根底にあるからではないだろうか。
5. 考察
痛みを訴える患者を治療する上で、とくに慢性痛においては、内服薬や神経ブロック等の処置を施しても、さらには心理療法などを加えたとしても、なかなかスッキリと完治して全く痛みがなくなることはあまりない。そこには医学的な(身体的な、心理的な)問題だけでなく、それ以外の、つまり社会的な人文的な要因も残されていると考える。それはヒトの長い進化過程の中で刻み込まれたもので、言葉で明確に表すことのできない領域、いわゆる無意識の範疇ということもあり理解し難い。その長い歴史の中でヒトに課せられた苦しみ、痛みは、密接な関係にもある二つの業苦(karma)となった。spiritual painとsocial painである。spiritual painはヒトが一人では生き抜くことができず、共助を不可欠とすることに起因し、social painはその共生とは反対側にある集団の掟に起因する。
spiritual painが問題となるのはどのような患者なのであろうか。科学や技術がここまで発展してきて、物質的にも恵まれた現代の生活は、昔の時代とくらべて格段に暮らしやすくなっている。現在のどこにそのような苦悩や痛みに関連する余地が人間に存在するというのか。それは、常に我々のつい傍に横たわっている。どんなに科学や技術が進展しても死は免れない。死に纏わるspiritual painは代表格である。死によってすべてを失う。今まで一人間として生きてきた証であり、存在そのものである人との間に築いてきたすべての関係性も失う。その怖れは計り知れない。
死ということ以外にも、同様に人との関係性がなくなることもあると考えられる。在宅患者や身寄りのない患者にその傾向があることをよくみてきた。神経変性疾患で臥床を余儀なくされベッドから離れられない患者、愛する妻が他界し生きる希望のなくなった患者、身寄りもなく若しくはあっても連絡の取れない状況で生活保護下に独居している老齢の患者。彼らは捕えどころがない痛みをいつも訴えていた往診患者であるが、内服も神経ブロックも心理療法も何も功を奏さなかった。どうすることもできず、ひと時ただ傍に居て話を聞くだけのために往診の形をとっていたに等しい。”Presence”というロジャースの言葉を胸に刻み、いつにか心が通じ合いどうにかなると信じていたがどうにもならなかった。二人は自殺という形に、一人も別の場所で不慮の死という結末となった。臨床能力の欠如や、患者管理の至らなさと言われればそれまでであるが、ただその当時にspiritual painについて理解があれば、また違う展開に多少なりともなっていたのではないかと今では思っている。ここでもやはり、真の意味での‘ふれあい’、‘つながり’が強調されてしかるべきであると考える。
social painとはどのようなものであろうか。
先ほど述べた科学技術の発展や豊富な生産体制が、ヒトにとっての幸せに本質的に成り得ているのか。もっと言えば農耕牧畜という定住生活をするようになったことが、それ以前の狩猟採集生活の頃より、果たして本当にヒトを幸せに導いたのか。狩猟採集生活の石器時代では、食物や天然資源が豊富にあり、争いやもめごともほとんど起こらず、少しの時間働くだけで、自由に暮らしていたといわれている。その生活様式で、ヒトは20万年近い長い期間を過ごしてきた。さらに言えば250万年前のホモ・ハピリスとして登場したとき、それどころか300万年前以上前のアウストラロピテクスの頃から、仲間と自然と調和して暮らし続けていた。しかし、およそ1万2000年前の気候変動とそれに伴う生態系の変化により、農耕牧畜による定住生活のはじまりが余儀なくされたと考えられている。そして紀元前9000年頃には中東全域に定住生活がみられ大きな共同体も形成されるようになり、以降町から都市へ、そして国家や文明が築かれることになる。長い人類の歴史からみれば、ごく短期間にかなりの環境変化が起きた。とくに産業革命以降、機械化、IC化など、さらに短期間に追い討ちをかけるように急激な変化となった。生物は何万年とか何百万年という長い時間をかけての環境変化には適応してきたが、短い時間の変動には絶滅も含めて適応が困難となる。social painとは、その急激な社会構造の変化に不適応に関連するものと考える。
social painと、人間関係からくるストレスなどに由来した痛みとは異なるのだろうか。当然、人間関係からくるストレスもsocial painに含まれる。それだけではなく、ほかにもさまざまな要素を含んだ、組織、集団に付随する痛みである。そこでは対人関係だけが問題になるのではなく、組織の制度自体や集団の雰囲気や存在から、ある意味哲学的問題までもが、個人を苦しめることがある。
具体例としては先ず、会社組織における人間関係上のストレスに関連した痛みや、家庭内の嫁姑間の嫁側におけるストレス由来の苦しみが挙げられる。両者ともその組織内ルールを強制的に上役から押し付けられる形で、誰が何のために考案したルールかなどはもはや関係ない。表面的に強制されなくとも、その構図は内在化されており、暗黙の了解のうちに従うことになっている。それは、姑が良い人であろうが悪い人であろうが関係なく、またルールが明文化されているかいないかも関係ない。なぜなら組織・集団の存続のために、ルールを裏切る行為をしたときや、組織のために役に立たないと、懲罰として痛みが与えられることを無意識的に内在しているからだ。そうして個人は、その組織・集団のワンピースとしての役割を与えられるのである。
これを当てはめれば、どんな組織・集団にもこの要素を含んでいることが推察できる。国家のような大きな組織から、学校の部活や近所の集会などの小さな集団、さらには家族単位やある友人との二人だけの関係までもsocial painは存在し得る。人は生まれた直後から、その国の一員として組み込まれている。そうすることで人間は進化を遂げ、発展してきた。その反面、その一員に対して制約と役割を暗黙のうちに強要している。生まれたときは誰もそのことを知らないが、教育という名のもとで、それが知らされる。そして、それが痛みを伴うものであることに気付くのである。そこで苦しみ、痛みを訴えるならば、先ほど述べたように、対人に問題があるからではなく、国家の制度もしくは存在自体に違和感を、内在的にも無意識的にも感じているのだろう。国家がなければ進化も発展もなく、その個人は存在しなかった。二律背反でもあるが、裏と表の関係でもある。
social painに対しては、組織・集団との関わりや距離感をいかにバランスよく取るかということになる。しかし義務や責任、規則、役回りなど既に組み込まれていて、なかなか抜け出せない、逃げられないから問題なのであり、どうすることもできない状況にもある。それに対して、抑圧、逃避、転移、否認、投影、同一視、取り入れ、合理化、反動形成、分離、退行、昇華、打ち消し、置き換え、補償、攻撃、自己への向き換え、逆転などの防衛機制が働くと考える。治療者側としては、それらを考慮した上で、患者に適する最善のコーピングを探し合っていくことになる。
実存主義のE.フランクルは、強制収容所のいつ処刑されるか分からないような夢も希望もないような状況でも、生きる意味の重要性を説いた。そのような凄惨な場面において、澄み渡る朝日の美しい光景や、仲間が台の上で唄うオペラの歌声が苦痛と苦悩の人々を感動させ、さらには脳裏に浮かぶ愛する家族への想いが生きる意味を与えたという。
実存主義のように愛や感動を以って生きる意味を説くことは、さまざまな領域において重要なことであると思われる。医療においても、診断や治療に留まらず幸せや感動を与えることの重要性は、全人的医療の観点からみてよく理解できる。殊に痛み治療の現場では、その重要度が高まるのではいだろうか。そこにはspiritual painとsocial painの問題が内在しているからだ。それは、個人レベルでも社会レベルでも、痛みの問題解決に重要な観点であると考える。
文献
1) Naito Yuji: A TENTATIVE PLAN TO THE STUDY OF INSTITUTIONAL CHILDREN: Investigation to Factors of Origination of Hospitalism:The Japanese journal of educational psychology 5(3), 32-40, 1958-03-25
2) Judith A. Turner, Joan M. Romano: Psychological and psychosocial evaluation. (John D. Loeser: Bonica’s management of pain, 3rd ed.). Philadelphia, Lippincott Williamals & Wilkins, 2001, 329-341
3) C. Richard Chapman, Judith A. Turner: Psychological aspects of pain. (John D. Loeser: Bonica’s management of pain, 3rd ed.). Philadelphia, Lippincott Williamals & Wilkins, 2001, 180-190
4) Eldon R. Tunks, Harold Merskey: Psychotherapy in the management of chronic pain. (John D. Loeser: Bonica’s management of pain, 3rd ed.). Philadelphia, Lippincott Williamals & Wilkins, 2001, 1789-1795
5) Wilbert E. Fordyce: Learned pain: Pain as behavior. (John D. Loeser: Bonica’s management of pain, 3rd ed.). Philadelphia, Lippincott Williamals & Wilkins, 2001, 478-482
6) Wilbert E. Fordyce: Operant or contingency therapies. (John D. Loeser: Bonica’s management of pain, 3rd ed.). Philadelphia, Lippincott Williamals & Wilkins, 2001, 1745-1750
7) Dennis C. Turk: A Cognitive-Behavioral Perspective on Treatment of Chronic Pain Patients. (Dennis C. Turk, Robert J. Gatchel: Psychological approaches to pain management: a practitioner’s handbook, 2nd ed.). New York, The Guilford Press, 2002, 138-158
8) Miki Osamu: The Clinical Feature of Depression with Psychosomatic Medicine in Primary Care:Japanese Journal of Psychosomatic Medicine 42(9), 585-591, 2002-09-01
9) 尾崎紀夫: プライマリケア医と精神科医の連携: 第129回日本医学会シンポジウム記録集 うつ病, 61-65, 2005
10) Patel V, Weiss HA, Chowdhary N, et al; Effectiveness of an intervention led by lay health counsellors for depressive and anxiety disorders in primary care in Goa, India (MANAS): a cluster randomised controlled trial: Lancet 2010 Dec 18;376(9758):2086-95.
がん患者と対症療法(2002),13,2,8
モダンフィジシャン(2003),23,3,314
Offer Bar-Yosef, ’The Natufian Culture in the Levant’ Evolutionary Anthropology 6(1998), pp159-77
Peter Bellwood, ‘The first Farmers’ Blackwell,2007