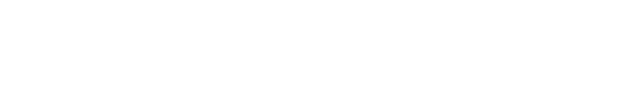首肩こり、肩甲骨内側のこり
主な治療方法
トリガーポイント注射
手技
首肩コリの場合、一般的にはトリガーポイント注射が行われます。何十年も前から行われて来ました。局所麻酔薬を痛みの部位に筋肉注射のようにうつだけで、危険性はほぼありません。正確に言うと、筋膜辺りに注射すると言われていますが、エコーで確認しているわけでもないですし、感覚で確実に筋膜に注射していると確実に分かるわけでもなく、ほぼ筋肉内に注射していると思われますが筋をほぐすということで意味はあります。
効果
効果は即効性がありすぐ分かりますが、数日もてば良いところで、当日のみや数時間ということもあり得ます。注射による注射部位の痛みだけが残り、あまり効果を感じなかったということも聞かれます。痛みがまた戻ってきたときも、以前よりは軽減されているということは期待ができます。
安全性
医療機関で受ける肩こり治療として、トリガーポイントブロックは危険性もほぼないですし、効果も出る人にはしっかり出ますので、最初に受ける治療としては適していると思います。
筋膜リリース(ハイドロリリース)
手技と効果持続期間
トリガーポイント注射では満足できない場合など、ひとつステップアップした治療として筋膜リリース注射があります。トリガーポイント注射と手技的には似ていますが、超音波画像を見ながら正確に針先を該当筋膜に置いて生理食塩水を比較的多く注入して、いわゆる筋膜を剥がします。トリガーポイント注射と筋膜リリース注射の両方してきた患者さん方に聞くと、筋膜リリースの方が長持ちするようで、1週間ほどとよく言われます。即効性で言えばトリガーポイントの方があるかも知れません、筋膜リリースは翌日くらいが一番効くとも聞きます。
リリース手技に伴う痛み
トリガーポイントが1か所数秒で終わるのに対し、筋膜リリース注射では超音波画像を見ながら針先を良い位置に持って行くこと、注入量も多いことから1か所10秒~1分ほどかかります。長時間針を刺し続けていると、痛みと緊張で迷走神経反射が起こり、一過性の脳虚血状態となりえます。ひどいと意識を失ってしまうこともごく稀にですがあります。
安全性
安全性については、その治療時間が比較的長く迷走神経反射を起こしやすいことを除けば、針先の確認と薬剤を使わないことからトリガーポイント注射より更に安全とも言えます。
筋膜リリース(ハイドロリリース)について詳しく
トリガーポイント注射と筋膜リリースとの比較
両者を経験した患者さんの評価では、中にはトリガーポイント注射の方が良かったと言われる方もいますが、9対1以上の比で筋膜リリースのほうが高評価でした。
首肩痛み部位別のリリース法
首の場合は板状筋、半棘筋の上下あたりを剥いでいくことが多いです。肩こりの場合は、主に肩甲挙筋と僧帽筋の間を、ときに棘上筋を狙います。
不慣れなマウスやキーボード操作をするなど手指をよく使うときに、肩甲骨内側あたりに痛みを生じることが多く、その際には菱形筋と僧帽筋の間をリリースしています。
最近では、前胸部の肩関節寄りの痛みに大胸筋/小胸筋間のリリース、前腕の肘寄り橈側の痛みに腕橈骨筋周囲をリリースして効果を出すことが増えてきました。頚椎症や胸郭出口症候群のような症状でも、実は筋膜由来の痛みがあることを経験しています。
その他にも、ふくらはぎや脊柱起立筋などにも応用できます。
さらにステップアップした首肩こり治療
星状神経節ブロック、硬膜外ブロック
トリガー、リリースでもいまいちで、次のステップとなると、星状神経節ブロック、さらには硬膜外ブロックが挙げられます。両者とも知覚低下を目的とした痛み治療ではなく、交感神経ブロックとしての側面を利用して副交感神経を優位に保つことで身体をリラックスさせ、血流を改善させることで、比較的長時間自己治癒に向かわせます。この交感神経ブロックというのが、痛みとくに慢性痛治療ではかなり重要となってきます。痛みが長く続く過程で、交感神経が関与されていて、そこを治療ターゲットとしないと、言い方を変えると痛みの神経(知覚神経)だけをターゲットにしていても、効果が一過性もしくは無効となることが多いです。
首肩こりの最上級治療:硬膜外ブロック
あらゆる治療を積み重ねてきた患者さんが最終的にたどり着くことが多いのが、硬膜外ブロックです。とくに線維筋痛症など難治性疼痛の患者さんでは、トリガーやリリースではあまり奏効せず、交感神経ブロックが効果をもたらすことがあり硬膜外ブロックでの治療になることが多いです。また、ストレス、不安、うつなどがベースにある首肩こりの方では、その痛み増悪や継続の原因として交感神経が関与していますので、必然として交感神経ブロックが重要となります。
肩こりボトックス
以上は保険診療での首肩コリ治療でしたが、自費診療になりますがお勧めの治療法が肩こりボトックス治療です。(筋肉を部分的に麻痺弛緩させることで、こりを解消させます。)
手技
当院では両側8か所に6単位ずつ入れて行きます。それでもまだ痛みが残る場合は1,2週あけてからまた追加することもあります。6単位と言っても液量で言えば、0.15ccというごく少量です。トリガー注射では0.5~1cclほど、リリースでは2~5ccと比べるとその少なさが分かります。
副作用
副作用として肩の重だるさ、腕の挙げづらさなどがありますが、この量では一般的にはあまり問題になることはありません。ただ、筋肉量の少ない方などでは必発します。
効果発現と持続期間
効果は数日後から出始めて1週間後にはほぼピークとなり、効果持続期間は4か月ほどになります。副作用はほぼ出ることはありませんが、出たとしても数週間で収まることが多いです。
エコーガイド下での注射
副作用はほぼないと言っても、適当に注射すればよいわけではなく、適切に注入することが求められます。というのも、肩こりの原因になりうるのは、筋膜リリースの際にも言いましたが、表面の筋肉より奥にあることが多いです。例えば肩こりの場合、表面の僧帽筋より、その奥にある肩甲挙筋がポイントになります。(もしくは僧帽筋と肩甲挙筋の間にある筋膜)。また皮下組織、僧帽筋の厚みは個人差があります(薄い人で1cm未満、厚いと2cm以上)。だから、やみくもにうってもなかなか良いポイントには当たりません。ボトックスの液体は少量とはいえ、拡散性が高いこともあり、副作用を減らす意味でも確実に当該筋肉の筋腹に注入することが求められます。現在では、筋膜リリースのようにエコーを用いることで確実にボトックス注射を行うことができるようになりました。
肩甲挙筋をターゲットにすることが重要
肩こりの場合、肩甲挙筋が関連することが多いです。比較的細い筋肉なので、あまり入れ過ぎると副作用の肩が重だるくなりますので筋肉量とのバランスが必要になります。また、僧帽筋の奥の比較的深いところにあるので、解剖的に熟知していても、エコーなしではなかなか確実に肩甲挙筋内に注射できません。超音波画像を見ながら、確実にボトックス6単位を筋の真ん中あたりに注入します。
美肩ボトックス
肩こりに併せて、同時に美容の要望(美肩:首を長く見せたい、肩をフラットにしたい)もあります。その際は僧帽筋のトップの面に片側3か所ほど入れています。肩の盛り上がりの筋肉部分は多少減らすことはできます。ただ、正面から見て肩盛り上がりの原因が、骨(第一肋骨)が上方に来ていることもあり、肩が盛り上がっているように見える場合には、おそらく満足するような美肩にはなりませんよ、と説明します。
首こりボトックス
首こりの場合は、板状筋や半棘筋に入れます。これも超音波画像を見ながら、肉厚の筋の箇所を探して、確実に筋腹の真ん中に入れています。筋膜リリースの応用ですが、コリのある部分は筋膜が肥厚、および血管新生が認められます。筋の厚みだけでなく、筋膜の厚さ、血管の有無などを評価して、該当する適切な箇所を狙って注射を行います。
肩甲骨の内側のこり
肩甲骨内側の場合は、僧帽筋に奥にある大小の菱形筋に、針が肺に刺さらないように超音波画像で注意しながら注射していきます。
その他の頭頚部ボトックス
その他にも、頭頚部こり痛みの部位に応じて、注射することがあります。胸鎖乳突筋、側頭筋、小胸筋などは比較的よく注射しています。
肩こりボトックスに伴う不具合
今までに1000回以上肩こりボトックス注射をしてきました。注射してしばらく肩が少し重かったと聞かされることはわずかにありましたが、大きな副作用はなく、ほぼ安全な肩こり治療と言えます。効果のほども、注射した部位に関してはほぼ100%近く効果をもたらしています。ただ、1,2週間後に、注射した部位と異なる場所が気になることはありえて、追加注射が必要なこともあります。
ボトックス製剤について
日本国内においてはA型ボツリヌス毒素製剤(商品名:ボトックス注用50単位・100単位)が注射剤として、1996年に眼瞼痙攣、2000年に片側顔面痙攣、2001年に痙性斜頚、2009年に2歳以上の小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴う尖足、2010年に上肢痙縮・下肢痙縮、2012年に重度の原発性腋窩多汗症の適応で承認されている。また最近、過活動性膀胱も適応承認されました。米国においては、斜視、痙性斜頸、眼瞼痙攣、上肢痙縮、多汗症に加え、神経学的疾患による過活動性膀胱、慢性片頭痛の適応で承認されている。
近年では医療用としてだけでなく、美容領域において筋弛緩作用を応用した「しわ取り」や「輪郭補正(エラ取り)」の目的で使用されていることが多いが、これらに関しては日本で保険対象ではない。
医薬品としての安全性
一般的にボツリヌストキシンの有害事象は一過性で、筋弛緩作用が強く発現したことによるものが多い。有害事象の多くは薬理作用の減弱とともに回復する。通常、医療目的では推定致死量の数百–数十分の一(注射にて換算)という微量を用いるが、用量設定を誤らない限りにおいては概して安全である。