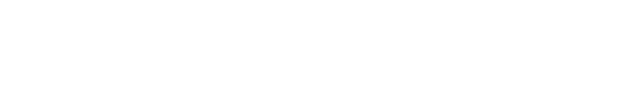在宅診療によりADLの改善
「非がん性慢性痛患者に対する在宅診療によって患者のADLは低下するか?」
要旨:慢性痛に対する治療としては、主に薬物治療(神経ブロックも含む)、心理療法、リハビリテーションなどが挙げられる。慢性痛治療ではADLを上げることが重視される。
在宅診療による患者のADL低下について、Graded Chronic Pain scale ( GCPS )を用いて評価した。
12名の在宅患者において、Pain intensityは半年後1年後に、7.1/10から6.3/10、6.0/10と低下する傾向であった。Disabilityも半年後1年後に、3.2/10から1.7/10、1.7/10と低下する傾向であった。
非がん性慢性痛患者に対し、在宅診療を行っても当該患者のADLは低下しない傾向にあった。むしろADLは改善される傾向にあった。また非がん性慢性痛患者に対しての在宅痛み診療により、痛みも軽減する傾向にあった。
はじめに
慢性痛に対する治療としては、主に薬物治療(神経ブロックも含む)、心理療法、リハビリテーションなどが挙げられる(図1)。慢性痛治療において、目的であり、とくに重要視されることがADLを上げることである。日常生活のなかで、どの程度自分で身の回りのことができるか、外出はどのくらいの頻度でどこまで行くことができるか、自分のやりたい事をどの程度まで実行できるかなどが評価される。
非がん性の慢性痛で在宅診療が必要となる患者では、ADLはもともと低いと言える。家の中をゴソゴソするくらいで、外出はほぼ不可能であったり、もしくは可能であっても外出しないということが多い。そのような患者でも、在宅診療が受けられない場合には、病院の日だけは外出する、逆に言えば外出するのは病院の日だけということがよくある。慢性痛治療の観点からすれば、理由はどうであれ、外に出ることは筋力維持の面からも、精神衛生上の点からも重要なことである。その唯一の外出の機会を、在宅診療を行うことにより奪ってしまい、結果的にそれがADL低下につながってしまっては、いわゆる逆効果となってしまう。
そこで、非がん性の慢性痛患者から往診の依頼があり、在宅痛み診療をすることになった際に、経時的にADLが低下しないかについて調べた。
- 方法
対象は、通院困難により往診依頼のあった慢性痛患者12名で、本研究の趣旨を文書で説明し同意を得た。
往診では外来通院時と同様の治療を継続した。
評価法として、海外にて慢性痛患者のADL評価としてよく使われている表1にあるGraded Chronic Pain scale ( GCPS )1)を用いた。全6項目の質問で、前半3項目は痛みの強度を経時的に評価するもので、後半3項目はADLを経時的に評価するものとなっている。 各項目とも0~10の11段階(0が良、10が不可)でのvisual scaleとなっており、これを往診開始時、往診半年後、往診1年後に、医師とは異なる第3者によりGCPSを日本語訳したものを用いて評価した。前半3項目を合算しPain intensityとして、後半3項目を合算しDisabilityとして評価した。Disabilityの低いほどADLは高いとして考える。各患者の各時点でのPain intensityとDisabilityの値を平均値として算出し評価した。両者とも低値ほど痛みは弱いことを、ADLは良好なことを表す。
- 結果
慢性痛で通院治療中の患者で通院困難による往診依頼のあった12名、男性6名、女性6名である。平均年齢は73歳(67~79歳)であった。疾患としては、慢性腰下肢痛(脊椎圧迫骨折後や脊椎術後の持続痛を含む)6名、脊柱管狭窄症4名、帯状疱疹後神経痛2名、頚椎・頚髄疾患2名、その他に視床痛、変形性膝関節症、大腿切断後幻視痛、閉塞性動脈硬化症、線維筋痛症、心因性疼痛などであった。尚、ここで挙げた疾患は、同一患者が複数の疾患をもっているケースがある。
治療については、内服処方は外来時と同様にできたが、神経ブロックや点滴においては安全性、衛生面の理由から外来での治療と比べ多少の制限があった。
GCPSのPain intensityとDisabilityについては、表2のとおりの結果を得た。Pain intensityは半年後1年後に、7.1/10から6.3/10、6.0/10に低下する傾向にあった。Disabilityも半年後1年後に、3.2/10から1.7/10、1.7/10に低下する傾向にあった。
- 考察
非がん性慢性痛患者に対し、在宅診療を行っても当該患者のADLは低下しない傾向にあった。むしろADLは改善される傾向にあった。また非がん性慢性痛患者に対しての在宅痛み診療により、痛みも軽減する傾向にあった。治療内容に関しては、内服薬の処方は外来と往診と処方する内容、数量ともに変化はなかった。往診によって、処方できる薬の種類や量を変える必要はないと思われる。ただ、神経ブロックなどの治療では、通院時より往診では治療に制限がされる。安全面、衛生面、器具の問題等の点から、在宅ではできず、院内でなければできないような神経ブロックや処置、点滴が存在する。ゆえに神経ブロックや処置については、院内で実施できる治療内容より、在宅でできる治療は劣る。それにも関わらず、ADLは改善し、痛みは軽減する傾向にあった。
がん性疼痛では、痛みを身体面だけでなく、心理面、社会面、スピリチュアル面から考える(図2)。同様に、在宅痛み診療を身体的治療以外の面から捉えてみる。非がん性慢性痛に対する在宅痛み診療の意義を、生物的モデル-心理的モデル-社会的モデルに分けて各々述べると、生物的モデルとしての在宅痛み診療の意義としては、痛みにより通院困難な患者が通院に伴う身体的・精神的負担や、診療待ち合いでの負担の軽減などが考えられる。ただここでは、先ほど述べた身体的治療のマイナス面や、外出の機会を奪ってしまうということも勘案し差し引かなければならない。
次に社会的モデルの点から考察すれば、通院される患者を診るのではなく往診をするということで医療者側が患者の環境、生活の一部となる。通院の患者においては、その環境や人間関係や生活様式を聞いた上で助言や指示を行っていたのに対し、往診して患家に入るということでその当事者となる。その現場のなかから環境調整、家族関係調整のアプローチを担うことになり、通院してくる患者から聞いていたこととは、また異なる状況が垣間見えてきたり、異なる方向へのアプローチが必要であると感じることもある。
つぎにとくに重要と考える心理的モデルについてである。当院においては、医師および臨床心理士が通院する慢性痛患者に対して、痛みに対する心理的アプローチを実施している。ここで、通院による心理的アプローチと往診で患家に赴いての心理的アプローチとの違いについてふれると、(1)認知行動的な側面からは、病院に通院するという負の強化によって維持された行動を消去できるということが考えられる。例えば、痛む患者が病院に行って神経ブロックの治療を受けると、痛みがすぐに軽減される。そうすると身体がそれを覚えて、反射的に病院=楽になるという図式となり、病院に向かうことが必須となり、ひどい場合は痛くなくても病院に行く、もしくは痛みではなく他の苦しみ(不安、だるさ、生活苦、ストレスなど)でも痛み治療の病院へ赴いてしまう。
(2)精神分析的な側面としては、しばしば「家=自己」と捉えられる。その患者の自己という場の中で、患者に接することができる。つまり家(の中)を見ること自体、その患者の無意識領域の解釈に繋がりうる。
(3)そして何より重要と考える支持的精神療法の観点から、その意義としては患者との治療関係、信頼関係を築きやすいことが挙げられる。心理療法のなかでどのような手技を用いるかなどよりも、なにより患者との治療関係を築くことが治療効果を上げるために重要とされている(図3)。在宅の場では、医師と患者との関係性に変化が求められることもある。一般の外来でのパターナリズムになりがちな関係性を、在宅での臨床の場にそのまま用いることはなかなか難しい。医師と患者間の関係性を、在宅診療に相応しいように変える必要があると思われる。しかし医師の方がそれにうまく順応できれば、治療関係としてはとても大きな効果を生じるはずである。
今回の非がん性慢性痛患者に対する在宅診療において効果を奏したのは、これら心理的アプローチ、とくに治療関係の向上に関連があったのではないかと考えている。
在宅診療を余儀なくされ痛みを訴えている患者の中に、スピリチュアルペインとしての問題を孕んでいることがある。むしろ外来患者と比較して在宅痛み患者に多く見られ、ある意味特徴的とも言えよう。落ち込みなどのうつ症状や不安、緊張など、その要因や状態が言葉で言い表し易い精神的不安定に由来した痛み(psychological pain)と異なり、スピリチュアルペインは無意識領域の問題でありそれ故に言語での表現はなかなか難しい。
たとえば、在宅診療を受けている痛み患者に、身寄りもなく人付き合いもあまりなかったり、介護サービスを積極的に利用しようとしなかったりすることをよく見かける。また、痛み(心因性も含め)があるからという場合もあるが、痛み以外の身体的障害により臥床を余儀なくされる患者もいる。その両者に共通しているのが簡単に言えば孤独感のようなものである。その孤独感を患者が実感して「孤独で寂しいなぁ辛いなぁ」と思い、それが痛みにつながればそれはpsychological painの範疇で、対応もわかりやすい。しかしそのような患者では孤独感を感じることはないと言い、一人で居るのが気楽と言い、誰の世話にもなりたくないと言う。そのように言葉には出していても(意識の領域で、頭で考えていても)、ヒトはそもそも一人では生きることができないように組み込まれていて、何かしらのアタッチメントが必要である。ホスピタリズムにあるように、ほかの人との触れ合いがないと生命の危機に陥るのである3)。頭では孤独でも大丈夫と考え、口に出していたとしても、無意識的にはその孤独感や触れ合いのないことを苦しんでいる、さらには痛みとして表出していることもあると考える。
そのような在宅患者に対しては、孤独感のようなもの、空虚感のようなものを感じ取って、何かしらのふれあいや絆を築くことが求められるのではないだろうか。その際に多職種の多くの人が関わることができると望ましい。なかでも患者にとって医師の存在は大きく役割も重要であろう。患者と可能な範囲でも時間をかけて向き合い、心を通わせることが求められる。
1) Von Korff M, Ormel J, Keefe FJ et al. Grading the severity of chronic pain.
Pain 1992; 50:133-149.
2) Lambert MJ. 1992 Implications of outcome research for psychotherapy integration. Handbook of psychotherapy integration; Basic Books; New York.
3) 内藤勇次. 施設児研究への一試案 : ホスピタリズム発生要因の追究. 教育心理学研究 5(3), 32-40, 1958-03-25
Does the ADL of non-cancer chronic pain patient decrease by the home medical care?
Torii Kei
Nagoya Pain Clinic
Abstruct
Treatment for the chronic pain mainly includes medical treatment (including the nerve block), psychotherapy and rehabilitation. It is a purpose in chronic pain treatment, and what is made much of in particular is to put up ADL. It is to improve ADL to be made much of in chronic sharp pain treatment.
I examined whether ADL did not decrease by at-home pain medical treatment.
By Graded Chronic Pain scale (GCPS), I examined whether at-home pain treatment reduced the ADL of the 12 patients.
Pain intensity tended to decrease to 6.3/10 from 7.1/10 a half year later, and to 6.0/10 one year later. Disability tended to decrease to 1.7/10 from 3.2/10 a half year later, and to 1.7/10 one year later.
For the non-cancer chronic pain patients, the ADL of the patients concerned tended not to decrease even if they are given at-home medical treatment. Rather the ADL tended to be improved. In addition, by the at-home pain medical treatment, the pain tended to be reduced.
Keywords: :home medical care, non cancer chronic pain , ADL
図3の説明
患者・治療外因子は基本的に治療を改善しても効果に変化が起こらない部分である。ここで治療効果に能動的に関係する因子は、治療関係と技法・モデルであるが、認知行動療法や力動学的精神療法や支持的精神療法の選択やその実施を適切に行うことよりも、患者-治療者の関係を良好にすることのほうが、治療効果をあげるうえでより重要な要素であることを示している。
図1
表1
表2
図2
がん患者の苦痛について
身体的苦痛
痛み
他の身体的症状
日常生活動作の支障
精神的苦痛 社会的苦痛
不安 全人的苦痛 仕事上の問題
いらだち (total pain) 経済上の問題
うつ状態 家庭内の問題
恐れ
怒り
スピリチュアルペイン
人生の意味への問い
価値体系の変化
罪の意識
死の恐怖
神の存在への追求
死生観に対する悩み
図3